元教育長の藤原義光氏による「島根の招魂祭」の書評
書籍紹介:「島根の招魂祭」戦役兵士はどのように祀られたか(有馬誉夫 著)
図書館に眠る新聞や郷土誌などを特定のテーマで丹念に拾い、そこに流れる歴史や、歴史の底流に流れている考え、思想を演繹的に浮かび上がらせる。
これが、有馬さんが独自に確立した歴史をひもとくオリジナルな手法だ。
今まで、この方法で明治以降の島根の観光レジャー史を2冊刊行している。
今回は、その観光史で取り上げた「聖地観光」、「遺族の靖国参拝」、「招魂式、臨時大祭」をまとめるときに目にとまっていた「招魂祭、戦没者慰霊」の資料を収集しなおし、1冊として上梓した。
筆者は、本書では自己の歴史観を封印し、新聞や郷土誌などに記載があった戦死、慰霊についての史実だけを淡々と丹念に書き進める。
これをどう読むかは読者の戦争観や歴史観でに委ねられているといえよう。そこで、ここからは私の“読み方”だ。
言わずもがなだが、「招魂祭、戦没者慰霊」は「職業軍人」も対象だが、多くは「国家の徴兵に応召し戦地で戦死した軍人を招魂し、慰霊すること」である。
そこには、必ず戦闘で血を流した累々たる若い死と残された遺族の存在がある。「招魂祭、戦没者慰霊」は、それを抽象化し、昇華し、英霊として慰霊する国家的宗教行事であり、戦意を鼓舞するものでなけねばならなかった。
しかし、社会的には抑えられた悲しみは次の記述が如実に語る。
戦士兵の父や母は健気に語る。「よく死んでくれました。今日あるは既に覚悟していたものと思います」「戦士は覚悟の上ですが、思ったより早く、充分な活躍が出来たか案じている次第です」
また、別の事例では、「夫をなくした妻が一粒種を抱き暗涙をおしかくしながらインタビューに答える側で母親は多数弔問者との挨拶に忙殺されていた」とある。
明治から昭和にかけての日本の近代化の歴史は、「西南の役」に始まり、日清戦争、日露戦争、満州事変、日中戦争、太平洋戦争とまさに「戦争の世紀」だった。太平洋戦争(範囲が明確でない)での日本人犠牲者数は外地での戦死や沖縄戦、内地での原爆や都市大空襲などの合計310万人だという。
日本帝国による侵略での中国、フェリピンなどの東南アジアでの犠牲者はもっと多い。
繰り返すが、戦争による死者、犠牲者は単に数字としてあるものではない。ひとり一人の個人の生命と尊厳が奪われた死の累計だ。
世界戦争としての第1次、第2次世界大戦での死者はさらにけた違いに多いという。
本書の招魂、慰霊からは「国家権力の行使による死屍累々」「国家と個人」の問題を感ぜずにはおれないのだ。
「島根の招魂祭」の紹介が山陰中央新報2020.6.22に掲載されました。
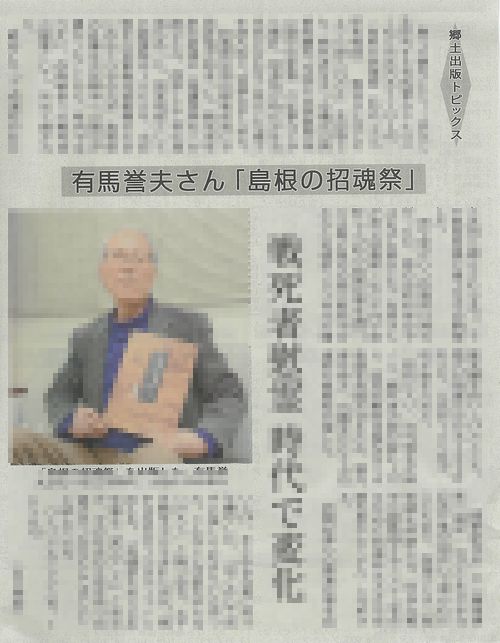
▼「島根の招魂祭」をアマゾンで買う。(品切れの場合はこちらからお問い合わせください。)
⇒ホームへもどる